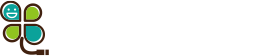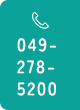潰瘍性大腸炎とは
 潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に炎症が生じ、びらん(ただれた状態)や潰瘍(傷)ができる原因不明の慢性疾患です。何らかの理由で免疫機能のバランスが乱れ、本来は外敵に対して働くべき免疫機能が自身の大腸を攻撃してしまう結果、大腸にダメージを及ぼす病態であることが分かっています。大腸の炎症は直腸から始まり、罹患範囲は全周性・連続性に大腸の奥の方へ進展していきます。また、治療を行って症状が改善しても(寛解)、再び悪化し(再燃)、それを繰り返すタイプ(再燃寛解型)が多いのも特徴的です。
潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に炎症が生じ、びらん(ただれた状態)や潰瘍(傷)ができる原因不明の慢性疾患です。何らかの理由で免疫機能のバランスが乱れ、本来は外敵に対して働くべき免疫機能が自身の大腸を攻撃してしまう結果、大腸にダメージを及ぼす病態であることが分かっています。大腸の炎症は直腸から始まり、罹患範囲は全周性・連続性に大腸の奥の方へ進展していきます。また、治療を行って症状が改善しても(寛解)、再び悪化し(再燃)、それを繰り返すタイプ(再燃寛解型)が多いのも特徴的です。
この病気を完治する治療法は現在も見つかっていないため、厚生労働省によって難病指定を受けています。日本では1970年代頃までは珍しい病気でしたが、平成28年度のデータでは約22万人の患者さんがおり、近年も増加し続けています。男女ともに20代に発症のピークがあり、若年者に多いですが、10歳代から、最近では中高年も含めた幅広い年齢層にも発症するようになっています。近年はこうした患者数の増加で注目を浴びるとともに医療の進歩によって、この病気に対する研究が盛んに行われており、最近10年間でも治療の選択肢が増え、以前と比べると病気のコントロールをしやすくなってきています。
原因
発症原因については未だ解明されておらず、自己免疫機能の異常、腸内細菌の関与、食生活の欧米化、遺伝、感染症など様々なテーマで研究が続けられていますが、明確な原因は特定できていません。
また潰瘍性大腸炎といってもひとりひとりが症状の程度や症状の経過、パターンは様々であり、軽症から重症まで、再燃・寛解を繰り返す人もいれば、ずっと安定している人もいる非常に多様性に富んだ疾患です。原因についても単一の要素ではなく、様々な要素が複雑に絡んで発症しているものではないかと考えられています。
症状
- 下痢
- 粘血便
- 腹痛(しぶり腹)
- 発熱
- 貧血
- 皮疹や関節炎
など
検査・診断
 症状から疑われたら、診断のために必要な検査として、便培養検査、血液検査、大腸カメラ検査を行い診断します。大腸カメラ検査の際は炎症を起こしている粘膜組織を複数個所で一部採取し、病理組織による評価も同時に行います。診断の際に重要なことは、潰瘍性大腸炎の症状は感染性腸炎と類似しているため、感染症の除外診断をきちんと行わなければならないという点です。
症状から疑われたら、診断のために必要な検査として、便培養検査、血液検査、大腸カメラ検査を行い診断します。大腸カメラ検査の際は炎症を起こしている粘膜組織を複数個所で一部採取し、病理組織による評価も同時に行います。診断の際に重要なことは、潰瘍性大腸炎の症状は感染性腸炎と類似しているため、感染症の除外診断をきちんと行わなければならないという点です。
また、発症からこれまでの経過で、初回発症型、再燃寛解型、慢性持続型に分けられます。
治療方針を決めるためには、様々なパターン分類を行います。自覚症状の程度や血液検査結果から、軽症、中等症、重症の3段階で病状の程度を評価し、内視鏡所見からも、軽症から重症までを把握します。また、罹患範囲別に、直腸炎型、左側結腸炎型、全大腸炎型に分けて考えます。
なお、採血でCRPという炎症を表す検査項目は、潰瘍性大腸炎では病勢を示す指標にはならず、症状が悪化していても、CRPは病勢と連動して上昇しないのは、クローン病と異なる点です。
治療
治療の考え方は、過剰に暴走した免疫を抑え込むというイメージです。従って治療のスタンスとしては免疫抑制治療が主体となります。症状が悪化している時に症状を改善し元の状態に戻す“寛解導入療法”と、無症状の状態を維持し再燃を防ぐための“寛解維持療法”の2つに分けられます。
当院はクリニックですので外来通院ができることが条件になります。従って、外来通院が厳しいほどの症状の場合(目安は中等症後半から重症)は入院治療が前提となりますので、入院対応が可能な専門の大学病院をご紹介いたします。そして入院治療により状態が落ち着いたら、再び当院で寛解維持療法を継続していく病診連携が可能となっております。
軽症から重症まで寛解導入療法の基本は、5-アミノサリチル酸製剤、通称”5-ASA(ごあさ)製剤”の内服治療です。剤型や薬の投与設計が異なるタイプが使用できます。軽症の直腸炎では5-ASAの坐薬製剤のみで治療が可能です。
必要に応じて局所療法(5-ASA製剤の坐薬や注腸製剤)を併用します。局所療法には5-ASA以外にステロイドの坐剤や注腸製剤、泡状のステロイド注腸フォームもあります。軽症や中等症の一部はこの5-ASA製剤の治療のみで寛解します。
それだけで改善しない場合は、中等量ステロイドの内服治療を行います。ステロイドの効果判定は1週間後に行い、症状の改善が得られていたら、1-2週間毎に少しずつ減量し、計3か月間でステロイド治療を中止します。ステロイドの減量中に症状が悪化することがあり、その場合は、GCAP(ジーキャップ)療法(白血球除去療法)を併用します。GCAPは血液透析を応用した治療法で、血液を体内から取り出し、血液中で過剰な免疫反応をしている白血球を専用の血液ろ過器でろ過し、きれいになった血液を体内へ戻すという治療です。治療は点滴を2本確保し、1回1.5時間の治療を週1回から週2回、計10回行います。GCAPのメリットは合併症がほぼなく、他の治療と異なり、副作用に感染症の危険性がなく安全であるという点です。外来通院でも対応できるため、入院を回避することができます。ステロイドあるいはGCAPで寛解導入できたら、その後も寛解維持療法として5-ASA製剤を継続します。ただし再燃する可能性が高い場合は、チオプリン製剤という免疫調節薬を内服し寛解維持をはかります。
チオプリン製剤は遅効型と言って、即効性はありませんが、導入3カ月目以降に再燃効果をもたらします。副作用に、導入初期で高熱、皮疹、関節痛、導入3カ月以内で白血球(好中球)減少、肝機能障害、導入2-3カ月目に脱毛、稀に導入初期に膵炎などが挙げられます。導入当初の3か月間は副作用が起きやすい時期なので、2週間毎に通院し、毎回採血検査と体調変化の有無をチェックします。現在はチオプリン導入前にNUDT15遺伝子多型検査を行うことが必須となっており、事前に副作用が起きやすい体質かどうかが予想できるため、副作用リスクが高い場合はチオプリン導入を見送るか、状況に応じて慎重に投与するかを判断することが可能となっています。投与量は少量から開始し、可能であれば徐々に増量し、以降は維持量を継続します。チオプリンを使用しても寛解維持ができない場合は、生物学的製剤という注射薬で寛解導入・寛解維持をはかります。
生物学的製剤とは、TNF-αという炎症物質を特異的に抑え込むことができる治療薬のことで、現在、インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブが使用できるようになっています。当院では主にアダリブマブを用いて治療を行っています。自己注射が可能なので、患者さんは自己注射の方法を覚えていただいて、自宅で皮下注射を行っています。ヒュミラで寛解維持中に、もし再燃したら、投与間隔を短くしたり、1回の投与量を増量したりして対応することが可能になっています。
そのほかにも最近数年で、抗α4β7インテグリン製剤のベドリズマブ(点滴製剤)、JAK阻害薬のトファシチニブ(錠剤)およびフィルゴチニブ(錠剤)も登場し、治療選択肢はさらに広がっています。
なお、あらゆる内科治療を行ってもコントロールがつかず、状態が悪化する場合は、外科的手術により治療します。手術は原則として大腸全摘出術です。人工肛門にするか直腸のごく一部を残して肛門機能を温存するか術式によって異なります。
潰瘍性大腸炎は完治こそできない病気ですが、適切な治療を続けて症状が落ち着いた状態(寛解)を維持することで、病気がない人と変わらない普通の生活を送ることが可能です。しかし、治療を継続しないと症状が悪化してしまうこと、長い間炎症が続くと大腸がんの原因にもなりますので、根気強く継続的に治療に取り組む必要があります。
クローン病について
クローン病とは、口から肛門までの消化管全域に炎症が起こり、びらん(ただれた状態)や潰瘍(傷)ができる病気のことです。潰瘍性大腸炎は似ていますが大腸だけに炎症が起こり、クローン病の治療においては食事療法が重要であるという違いがあります。発症の原因は解明されていませんが、何らかの理由で免疫のバランスが乱れ、全消化管に自らの免疫機能が暴走して傷つけてしまうことが分かっています。潰瘍性大腸炎と同じく国から難病指定を受けています。また、厚生労働省のデータによると、日本においては約40,000人の患者さんがいると言われており、年々患者さんの数は増え続けている傾向にあります。
原因
発症の原因は解明されていませんが、何らかの理由で免疫のバランスが乱れ、全消化管に自らの免疫機能が暴走して傷つけてしまうことが分かっています。
症状
下痢や腹痛が現れますが、最も特徴的な症状は体重が著しく減少することです。また肛門の痛みや腫れが生じますが、通常の痔よりも治りにくく悪化しやすいのも特徴の一つです。
- 腹痛
- 下痢
- 体重減少
- 肛門の痛みや腫れ、白い膿の排出
- 口内炎
- 発熱
- 貧血
- 消化管狭窄(きょうさく)・腸閉塞
- 消化管穿孔(せんこう)
- 腹腔内膿瘍(ふくくうないのうよう)
- 皮疹
- 関節痛
など
検査・診断
 自覚症状からクローン病が疑われたら、血液検査や便培養検査、腹部レントゲン検査や大腸カメラ検査を行います。ただし、複雑痔瘻(じろう)や肛門周囲膿瘍(のうよう)で肛門痛がつらい場合は、先に肛門治療を優先してから、落ち着いたところで大腸カメラ検査を行う場合もあります。その場合は肛門外科をご紹介します。また初診の段階で、腹腔内膿瘍の可能性が疑われる場合はCT検査が必要となります。
自覚症状からクローン病が疑われたら、血液検査や便培養検査、腹部レントゲン検査や大腸カメラ検査を行います。ただし、複雑痔瘻(じろう)や肛門周囲膿瘍(のうよう)で肛門痛がつらい場合は、先に肛門治療を優先してから、落ち着いたところで大腸カメラ検査を行う場合もあります。その場合は肛門外科をご紹介します。また初診の段階で、腹腔内膿瘍の可能性が疑われる場合はCT検査が必要となります。
診断自体は大腸内視鏡検査を行い、特に回盲部(小腸と大腸のつなぎ目付近)を中心にクローン病に特徴的な縦走潰瘍や敷石像といった内視鏡所見を確認できれば概ね診断は確定できます、また、大腸カメラ検査の際に粘膜の一部を採取して病理検査を行い、クローン病の診断に役立つこともあります。しかし、大腸には病変がみられず、小腸や上部消化管だけに異常を呈するタイプもあるのと、大腸のみならず、小腸の炎症所見の程度で治療方法も変わってくるため、クローン病全体の状態評価のためには小腸内視鏡検査やCT検査が必要です。
小腸内視鏡検査やCT・MRI検査ができない当院では、初診の段階か、大腸カメラ検査を行った段階でクローン病が疑われた時点で、専門の大学病院をご紹介しています。治療が行われ、病状が安定している場合に、病診連携として、当院で定期採血や維持療法を担当することは可能です。その場合、定期的な小腸検査や検査結果評価に基づく治療内容の変更は専門医療機関で行っていただきます。採血で測定するCRPという炎症を反映する検査項目は様々な病気でも異常を示しますが、クローン病の場合は病気の活動性を示す指標としても利用できるため大変役立ちます。
治療
 クローン病は治療で完治することは難しく、治療で病状を安定化させコントロールすることで生活の質(QOL)を維持することが第1の目標であり、治療の基本は食事療法と薬物療法です。また、クローン病は生涯の中で少なくとも1度はおなかの手術を行うことが多いです。病状の経過によっては何回も手術を繰り返さなければならない場合もあります。必要な時に手術は大切ですが、内科治療によって、できる限り手術を回避できるように病状を抑えることも重要な第2の目標と言えます。
クローン病は治療で完治することは難しく、治療で病状を安定化させコントロールすることで生活の質(QOL)を維持することが第1の目標であり、治療の基本は食事療法と薬物療法です。また、クローン病は生涯の中で少なくとも1度はおなかの手術を行うことが多いです。病状の経過によっては何回も手術を繰り返さなければならない場合もあります。必要な時に手術は大切ですが、内科治療によって、できる限り手術を回避できるように病状を抑えることも重要な第2の目標と言えます。
食事療法は、脂肪が消化管に過剰な免疫異常を引き起こす誘因となることから、低脂肪の食事メニューにする必要があります。具体的には、ラード、バター、肉の脂身などの飽和脂肪酸、マーガリン、ごま油、大豆油、コーン油などのn-6系脂肪酸は炎症を悪化させるため極力控え、EPA、DHAを多く含む魚や、えごま油、菜種油などのn-3系脂肪酸は炎症を抑えるため積極的に摂取します。また、食事以外にエレンタールという栄養剤を服用すると、それだけで自覚症状が改善され、栄養も補えるため、体重を増やすことも可能となります。特に小腸狭窄を伴っている場合は腸閉塞を起こしやすいため、繊維質の多い野菜や根菜類、キノコ類、こんにゃくなどの消化に悪い食材は日頃から避けておく必要があります。
薬物療法では、5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA(ごあさ)製剤)を基本薬とし、病状に応じて免疫調節薬や生物学的製剤という注射薬を用いて、病状をコントロールして再燃を予防します。症状が強い時は、副腎皮質ステロイドを用いて寛解導入療法を行います。ステロイドは急性期のみ有用であり、長期に服用すると再燃予防効果がないばかりか副作用も懸念されるため、使用後は徐々に減量中止にしていきます。
肛門病変は薬物治療だけでも改善することがありますが、原則として肛門外科による管理が必須です。肛門周囲膿瘍(のうよう)の場合は膿瘍を切開します。複雑痔瘻(じろう)に対してはシートン法と呼ばれる手術療法を行います。
また、クローン病特有の合併症として、時に突然激しい腹痛や腹部膨満・嘔吐を生じたり(腸閉塞)、突然激しい腹痛と発熱を伴う消化管穿孔(せんこう)・腹腔内膿瘍(ふくくうないのうよう)を生じたりすることがあります。その場合は救急車を要請のうえ大学病院へ緊急受診してください。外科による緊急手術治療が必要となることが多いです。
クローン病は発症すると一生のお付き合いとなる病気です。本人自身が病気を理解し受け入れるだけでなく、家族や友人、恋人や生涯の伴侶、職場の人間など、周囲の人たちの病気に対する理解も不可欠です。若い時に発症することが多いため、学業やスポーツ活動、進学、就職活動、結婚、出産など人生の重要なライフイベントに重なってきますが、適切に治療を継続することで、症状が安定するだけでなく、より人生を豊かに暮らしていくことができるようになっています。
当院では専門の大学病院との病診連携を取りながら、維持療法や生活相談などのサポートを行っていくことが可能です。